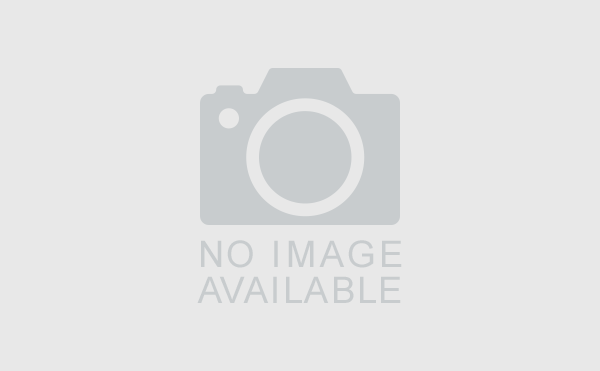インターネットと私たち
【ネットが普及してすでに久しいですが、なんとまあ、うるさい世の中になったものよ、と嘆かざるを得ません。昔はもっともっと静かでした。いったいなぜこんなことになってしまったのでしょうか。じっくり考えてみたいです】
知る人「君が懐かしさを覚える<昔>とは、インターネット普及以前だよね」
問う人「ええ、言うまでもないです。20世紀終盤あたりでしょうね」
知る人「表計算の縦計と横計の違いという難所からロータスが救ってくれた時代だな」
問う人「そうそう、そうです。あの頃が懐かしいですね」
知る人「君の話で、あることを思い出したよ。その昔、東京の墨田川では、夏になると泳げたそうだ。当時の子供たちは、夕暮れまで川遊びに興じていた。のどかな光景だっただろうね」
問う人「なるほど、僕の言うネットの普及は、それと根っこのところでつながっている、と言いたいわけですね」
知る人「そういうことだ。泳ぐのが不可能なほど川が汚れた理由は、戦後の経済成長だった。より良い暮らしのために、清涼な川の水が犠牲になったのだな」
問う人「そういうことですね。誰とでも即つながる情報化社会を築くためには、今の騒々しい世の中になることは避けられなかった、ってところですかね」
知る人「おっしゃる通りですな。それだけ物分かりが良ければ、ここに来る必要はなかっただろう」
問う人「いやいや、ここからですよ。なぜうるさくなってしまったのか、その原因を突き止め、悪をもとから絶たなきゃだめでしょ」
知る人「君は隅田川の話を理解していないようだな。当時、なぜ川の水がきれいだったか。理由はただ一つ、汚す必要がなかったからなのだ。美しい川を守ろうとしたのではない。たとえ戦前であっても、必要とあらば今のような汚水となったであろうな。その時代はまだ他のことで忙しくて、川の利用まで手が回らなかっただけだ。つまりだな、川水の汚染まで、ほんの数歩の位置にいたのだな、当時の社会も。インターネットの話も同じだよ。ネット環境が未整備だったから世の中が静かだったのではない。昔から言うであろう、『人の口に戸は立てられぬ』と。しゃべりたくてうずうずしている輩、手近なところで喋りまくっていた輩ならば、大昔からいたのだよ。ただ、それが今のように瞬時で伝わってこないから、当時が静かな時代だったかの如く錯覚を起こすのだ。よいか、われら人間というものは、太古の時代より現在に至るまで、本質的には変わってはおらぬのだよ。ネット環境さえあれば、縄文時代から日本はうるさかっただろう。文明とは、良くも悪くも、われらを助けてしまう。その結果として環境が悪化する。インターネットの劇的な普及が騒々しい社会を生み出したのではなく、じゅうぶんその下地が育っていたところにネット網が張り巡らされたのだ。いつの世も、原因を作るのは私たち自身であって、私たちの作った道具が独り歩きするわけではないのだよ」
(了)1206字