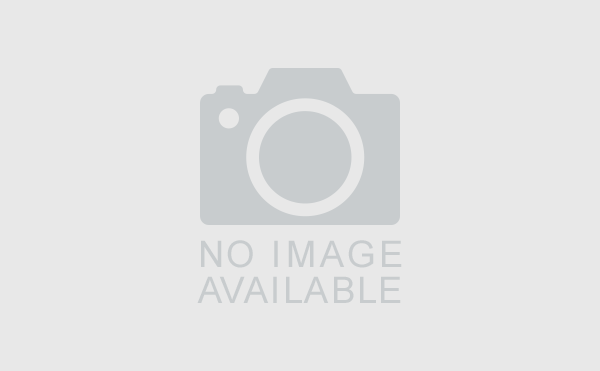軽くて便利、カタカナ日本語
【NHKの番組を観ていたら、『アート』という台詞が何十回も出てきた。美術館の場面だった。すっかり辟易してしまい、テレビを消した。『芸術』ではダメなのだろうか。われら日本人の特徴として、あきらめるしかないのか】
問う人「某直木賞作家が、『イン・ザ・メガチャーチ』という題の本を出しましたが、あれも似たようなものでしょうか」
知る人「まあ、そんなものであろうな。学生みたいな面構えの青年作家だからな、英語が和語を浸食してゆくのに、まったく抵抗を覚えぬのであろう。当サイトの如き視点は、彼らからすれば、時代遅れのじいさんばあさんのたわごとに違いあるまい」
問う人「このサイトでは、過去に何度も論じられましたよね、母語の乱れについて」
知る人「そうだな。こういう場合、かつては記事内にリンクを貼り、当該記事へと誘導したものだが、近ごろはそこまでやらぬ。気になるなら自力で探せばよかろう」
問う人「そうですか。まあ、誰も読んでいない開店休業サイトですから、それもいいでしょうね」
知る人「カタカナ語を伏せ字にしたらまったく意味が通らなくなる文章の、なんとまあ多いことよ。もはやなすすべなしだな。母語はその民族の礎であり、絶対に失ってはならぬ貴重な財産のはずなのだが、一億総消費者と化したわが国では、母語でさえ消費の対象なのだ。誰も見ていないこの場でいくら論じたところで、何の意味もない。が、表題については、いちおう論じておいたほうがよかろう」
問う人「軽くて便利なカタカナ語、という言葉の意味を知りたいものですね」
知る人「冒頭に出た『アート』を例にして考えてみよう。日本語なら『芸術』だが、番組のどこにもそれは使われなかった。カタカナ語で統一されていたようだ。まあ、途中で消してしまったから、あるいは後半に和語が使われたのかもしれぬが。それはそれとしてだな、なぜ『アート』なのかと問われれば、理由はおもに二つだ。
1)現代人の耳に馴染んでいるから
2)手軽で使いやすいから
・・・どちらも同根の問題だから、まとめて論じよう。芸術と聞いて、何を連想するかね」
問う人「そうですねえ。人によるとは思いますが、美術で言うなら、棟方志功か狩野探幽、運慶快慶、ゴッホにピカソ…」
知る人「はじめに紹介した直木賞作家はどうだろう。鷗外やトルストイの隣にいるのは身の程知らずでも、『アーティスト』と呼ばれる者どもの集団の中であれば、さぞかし居心地がよかろうね」
問う人「いわゆるJ-POPとかいう連中が、『ぼくらアーティストは…』なんて喋っているのをよく耳にしますが」
知る人「そうだろう。彼らがもしも『ぼくら芸術家が…』と語れば、ベートーベンやモーツァルトの系譜に立たねばならなくなる。いくら厚顔無恥の現代青年たちでも、それは場違いなこととわかるだろう。ところが『アーティスト』と自称した途端、同類のお仲間が増えるのだな。そこは彼らにとって実に快適な空間なのだ。なんとなく芸術家でいられるのだからな」
問う人「なぜそのように意味が違ってくるのでしょうね、和語とカタカナ語では」
知る人「もとは同じだからな、要は使い方の問題だろう。舶来文化への憧憬は、二千年も続いてきた感情であり、精神状態だ。これに従って言うなら、芸術をアートと言い換えるなど些事に過ぎまい。日本語の意味をあいまいにぼかすことで、『芸術』に抵抗を覚えていた層をも取り込んでゆける。また、常に舶来ものを上位に置きたがるわれらの精神構造は、外来語には、日本語にはない深い意味があって云々、とやり出す始末だ。日本語では表現しきれないなどと平気で言う学者や文化人もいるが、それは日本語の持つ深い意味を探ろうと努力してこなかったからなのだ。考えてもみよ。英語やドイツ語に深い意味があるのなら、われらの母語も同様であろう。なぜ欧米ものの後塵を拝したがるのだ。長くなったからもうやめるがね、『芸術』を『アート』と言い換えるのは、常に西洋を優れた世界と盲信してきたわれら島国人の、あしき伝統なのだよ。世界の中心を欧米に置く精神構造をあらためない限り、芸術が芸術と呼んでもらえる日は来ぬであろう」
(了)
1703字